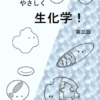7 各論2:脈・血圧(血管):高血圧・低血圧(3)輸液(2)
等張液輸液は、細胞の中に無理やり入り込むものでも
細胞の水を奪うものでもありません。
とても便利ですが…
エネルギーのもと(糖質)も欲しいですね。
そこで生まれたのが低張(電解質)輸液。
ブドウ糖(グルコース)が入った輸液で、
最初は輸液全体が
ヒト細胞と等張液になるように作ってあります。
グルコースは代謝されると、
水と二酸化炭素とATPになりますね。
最終的はグルコースの粒が減って水が増えますから、
低調(浸透圧が低くなる:薄くなる)液になります。
個別の目的に合わせて作られた
1号液から4号液が使われます。
「まず水の補給!どこが悪いかはその後で!」
こんなときに使うのが1号液。
ナトリウムイオン(Na⁺)と塩化物イオン(Cl⁻)の濃さは薄めで、
カリウムイオン(K⁺)を含みません。
電解質(イオン)はいじらずに、
水分補給で落ち着いてくれればオーケー。
もしだめなら、ちゃんと原因を探してから次の輸液にうつります。
「脱水だ!」と分かったときに使うのが
2号液(「脱水補給液」)。
ナトリウムイオンと塩化物イオン、カリウムイオンに加えて
マグネシウムイオンや乳酸イオン等も含みます。
細胞内液補給に重点を置いた輸液ですね。
「脱水」と簡単に言いましたが、
脱水にも種類があります。
炎天下や食事をとれない体調不良のように、
じわじわと水分がなくなった脱水は
細胞外(血液・組織液)だけでなく細胞内水分も足りません。
そんなときに細胞内に水分を届けるときに使うのが、
2号液になります。
2号液で水・電解質不足が落ち着いたあとに使うのが
3号液(「維持液」)。
こちらは2リットルあたりに1日必要量相当の
ナトリウムイオンと塩化物イオン、
カリウムイオンを含んだもの。
お目にかかる機会が一番多い輸液です。
水分の体へのイン・アウトのおはなしは、
生化学でミネラルの前提としておはなししてあります。
とりあえず「飲料水と食物中の水」の部分が
この3号液2リットルに置き換わったと思ってくださいね。
手術をすると、
たいてい水分が足りなくなります。
普段水分や熱が逃げないように
覆ってくれる皮膚を切って、
出血のある手術をする以上、
どんなに注意しても仕方のないことです。
だから、手術後の水分回復に使うのが
4号液(「術後回復液」)です。
こちらは細胞外液が足りなくなる急な脱水です。
似た状況には嘔吐や下痢も当てはまりますね。
成分はナトリウムイオンと塩化物イオン、
ブドウ糖(グルコース)と乳酸イオンで、
カリウムイオンは入っていませんよ。
このように分かれてはいますが…
主に使われるのは1号液と3号液です。
目的とする状況の違いは分かってもらえたと思いますが、
「1号液にはカリウムイオンが入っていない」ことは
ポイントですからね。
【今回の内容が関係するところ】(以下20221226更新)