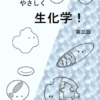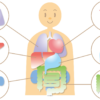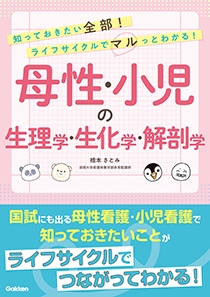1 解剖生理学を勉強する理由(3)
「ヒトは、どうすれば生きていけるでしょうか?」
ここまで読んできた今の皆さんなら、
答えることができますね。
心臓が動いて(循環器系)、
息ができて(呼吸器系)、
食べ物を食べられて(消化器系・泌尿器系)、
ちゃんと寝ることができる(神経系・内分泌系)…
これらが、生きるために必要な
「正常」でいるための働きです。
さらっと泌尿器系が追加してあることに気付きましたか?
食べ物は、食べるだけでは不十分。
食べ物の残りかす(栄養物を吸収して終わった後)は、
ちゃんと外に出さないと
次の栄養物を入れることができません。
「大事なものだ!」と
いろいろなものを取っておいたのでは、
部屋の中に新しいものを入れる場所が
なくなってしまうことと同じです。
水に溶けない残りかす「便」は、
消化管から外に出します。
水に溶ける残りかす「尿」を排出するためには、
泌尿器系の働きが必要です。
そして、先に挙げた器官系は
「必要最低限」にしかすぎません。
骨格系がないと、軟体動物状態です。
生殖器系がないと、
子孫を残すことができません。
だから、どうしても解剖生理学は
勉強することが多くなってしまうのです。
「正常」を知るために。
ヒトがヒトとして生きていくために。
次回から本格的に始める解剖生理学のおはなしは、
先に出た必要最低限の器官系を勉強して、
それから残りの器官系の勉強と進めていきます。
呼吸器系→循環器系→消化器系と泌尿器系→
神経系と内分泌系のあとに、
筋骨格系と生殖器系のおはなしですね。
大事なことは先に言っておきますよ。
それぞれの器官・器官系は
独立して存在しているのではありません。
常に、他の器官系と関連しあっています。
最初の質問
「ヒトは、どうすれば生きていけるでしょうか?」は、
突き詰めれば
「細胞は、どうすれば生きていけるでしょうか?」と
同じ質問です。
だって、ヒトは多細胞生物。
細胞が生きていけないなら、
ヒトとしても生きていけないのです。
だから、生物や生化学とかなり深く関係しています。
できるだけ「どこどこと関係しているよ!」と
注意喚起していくつもりですから、
必要に応じて、
生化学の対応するところも読み直してくださいね。
ものごとは、正常に(問題なく)動いているときは
その重要性に気付くのが遅れます。
ヒトの体も、どこか不具合が出ないと
健康のありがたみが分かりません。
そんなことになる前に、
「正常」の重要性を理解しましょう。
生化学もそうでしたが、
解剖生理学を勉強することは自分の健康維持にも役立ちます。
「何の役に立つのさぁ!」の理由には、
「看護師国家試験の必須科目だから」、
「正常を知るため」だけではなく、
「自分の体を知り、健康でいる」ことも
含まれることを忘れずに!
【今回の内容が関係するところ】(以下20220813更新)