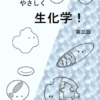7 生殖器系のおはなし(8)
性感染症のおはなし、一段落。
今回は女性ホルモンの2相性のおはなしです。
この2つの相がないと、妊娠できません。
つまり、新しい生命が産まれないということです。
2種類の女性ホルモンと、
黄体形成ホルモン(LH)が主役のおはなしですよ。
ホルモンの説明自体は
生化学「11 ホルモン」でしましたね。
卵胞ホルモンと黄体ホルモンがあること、
2つのホルモンは分泌量が変化して、
そのせいで体温の高温相と低温相ができることはおはなししました。
相の切り替わりは、排卵と月経。
排卵のきっかけは、
黄体形成ホルモン(LH)の急上昇「LHサージ」です。

このLHサージで、黄体ホルモンが増えだします。
「卵子が卵巣から出たから、
いつ受精卵ができるかわからない。
子宮内膜と乳腺育成しておかなくちゃ…」
よく気の利くホルモンですね。
各種準備のために体内水分量は多めになります。
受精卵が成長しやすいように、体温は高めに保っています。
「高温期」ですね。
受精卵が来たら育てる気満々のモードです。

でも受精卵が一定期間内に来なかったら、
子宮内膜はお役御免です。
また新しい子宮内膜を準備するために、
古くなってしまった子宮内膜をはがします。
これが月経。
このころになると卵胞ホルモン分泌量が増えてきます。
「さあて、卵子の1つを成熟させて排卵まで待ちますか…」
こちらは卵子育成に集中するので、
体温は低くても大丈夫。「低温相」です。
まとめておきましょう。
女性ホルモンには卵胞ホルモンと黄体ホルモンがあります。
卵胞ホルモンが多いときには、
卵子育成に励む低温相。
黄体ホルモンが多いときには、
受精卵が来た時に備える高温相。
LHサージのショックで排卵が起きると、
黄体ホルモン優位の高温相に。
月経で子宮内膜が剥がれ落ちると、
卵胞ホルモン優位の低温相になります。
この2つの相がないと、排卵がなく、
受精しても育成できる環境になりません。
だから妊娠を希望する人は、
基礎体温を測定することになるのです。
生化学「11 ホルモン」でこの話をしたときは
「へえー、なんだか面倒なんだねー!
『LHサージ』って言葉だけ覚えておけばいいんだねー!」
…ぐらいだったと思います。
でも、ここまで生化学と解剖生理学を勉強してきた今なら、
「…だからLHサージって大事だったんだ…
受精卵の細胞分裂、大変だもんね…
ちゃんと受け止めなくちゃ…」
と思ってくれるはず!
次回から、今までの勉強の総復習にもなる
「発生概論」のおはなしです。
【今回の内容が関係するところ】(以下20221025更新)