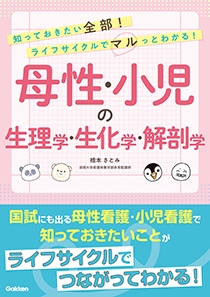9 各論4:体温(内分泌系):甲状腺・副甲状腺(8)
エストリオールの慎重投与。
https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00052360
禁忌から簡単に想像できるものが大半ですが、
全身性エリテマトーデス(SLE)、
てんかん、糖尿病の文字もありますね。
糖尿病については、
併用注意に血糖降下剤の一部があることからも分かるように
「細胞の糖に対する反応(耐糖能)」が変化するから。
全身性エリテマトーデス(SLE)は
次の「感染・免疫」のところでおはなしする自己免疫疾患。
てんかんは脳(の神経細胞)が
変な電気発生を起こしてしまったものです。
全身性エリテマトーデスは
自分の体を「異物!」と認定してしまった結果、
腎臓の糸球体に抗体等がたまって(免疫沈着物質)
腎臓がうまく働かなくなってしまいます。
その結果むくみやだるさが出るのですが、
卵胞ホルモン補充でこの症状が悪化してしまう恐れがあります。
てんかんは神経細胞の異常な電気発生(神経興奮)が原因。
卵胞ホルモンは一般的に神経を興奮させる方向に働きます。
また、心臓や腎臓の病気(既往を含む)によって、
体の中に水分がたまりやすくなり(体液貯留)、
そのせいでミネラル異常から
電気発生異常が起こりやすくなります。
これもてんかんを悪化させる原因になりますね。
骨の成長が止まっていない可能性のある人や
思春期前の人も慎重投与対象ですよ。
骨端線のおはなしは、
副甲状腺ホルモン補充製剤のテリパラチドで出てきました。
骨の成熟は卵胞ホルモンの得意分野。
骨芽細胞を応援して、
骨にどんどんカルシウムを埋め込ませます。
破骨細胞は抑制しますから、
「今の骨の形」はあまり変わりません。
だから骨の成長が止まる(=骨端線早期閉鎖)のです。
思春期前に卵胞ホルモンを補充すると
性的早熟の可能性があります。
「性的早熟」とは、
心身共に準備が完成する前に第二次性徴が始まってしまうもの。
小学校に入ってすぐに乳房成長、月経開始…では、
いらぬ不安や仲間外れの原因になりかねませんからね。
黄体ホルモンや男性ホルモンの補充は、
「骨(の強度)」にそこまで直接的影響はありません。
ですから、このあとの「副腎・性腺」のところにまわしますね。
【今回の内容が関係するところ】(以下20230404更新)