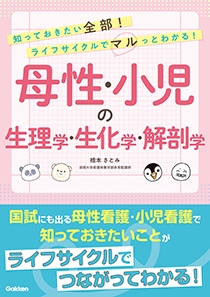2 呼吸器系のおはなし(10)
「筋肉がちゃんと収縮しているか」という問題を、
反射と呼吸中枢のおはなしから理解できましたね。
もう、呼吸に必要なものは理解できたはずです。
…そもそも、
どうして呼吸できなきゃいけないんでしたっけ?
呼吸をすることで、酸素と二酸化炭素を交換して
全身の細胞に酸素を届ける必要があるからでした。
細胞が十分なATPを作ることができなければ、
心臓の筋肉も、消化器官の筋肉も動きませんからね。
もちろん神経細胞が判断するにも、
情報伝達するにもATPは必要ですよ。
ここでちょっと考えてみましょう。
明らかに呼吸が苦しそうな人がいたら、
その人(の細胞)は酸素不足ではないかと
予測できますよね。
具体的には、呼吸数がやたらと多い、
肩を使って努力呼吸をしている状態です。
これはすぐに気付けますね。
じゃあ「見た目が問題なさそうだったら
常に酸素は十分」でしょうか?
答えはノーです。
一見何の問題もなさそうでも、
実は細胞が酸素不足で助けを求めていることがあります。
…早く細胞の酸素不足を何とかしてあげたいところですが、
どうすればそれに気付けるでしょうか?
そこで出てくるのが「パルスオキシメーター」です。
指先をやさしく挟み込む小さな器具で、
病院実習で見ることができますよ。
実習先によっては、毎日使うことになるはずです。
指先につけて10秒ほどで、
デジタル画面に数字が出てきます。
これは「経皮的動脈酸素飽和度(SpO2)」という数字です。
パルスオキシメーターは爪先の血管に光を当てて、
血液中のヘモグロビンが
どれくらい酸素とくっついているかを見ているのです。
ヘモグロビンは酸素を運ぶ赤血球の中にある色素のこと。
酸素とくっつくと鮮やかな赤に、
酸素とくっついていないと暗い赤になります。
パルスオキシメーターは簡単で、
痛みもないのでとてもよくつかわれます。
健康な人でも、100%になることはありません。
98%ぐらいなら
「細胞に届ける酸素には問題ないよー」という状態。
95%を切ると「…ちょっと苦しくなってきたかも…」、
90%を切ったら「早く何とかして!」という状態です。
うまくガス交換ができない状態になれてしまっていると、
患者さんに「苦しくないですか?」と質問しても
「別に苦しくないよー」と
答えが返ってくることもありますが…
細胞レベルでは明らかに酸素不足です。
パルスオキシメーターによる計測は、
マニキュアや指先の血行不良の影響を受けます。
マニキュアは
「爪に色が付いたら、色素が良くわからない!」と
すぐに気が付けるはず。
気温が低いときの指先血行不良は
忘れられがちですので、気を付けましょうね。
【今回の内容が関係するところ】(以下20220822更新)