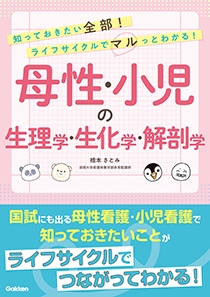2 呼吸器系のおはなし(9)
反射について分かったところで、
呼吸をコントロールしてくれる呼吸中枢のおはなしです。
反射は「受容器→中枢→効果器」の流れでしたね。
効果器にあたるのは、以前確認した呼吸筋群です。
命令を出す中枢は1つですが、
受容器が2種類ありますから、そこに注意ですよ。
まず、橋や延髄に
二酸化炭素化学受容体というものがあります。
延髄は首と頭のつなぎ目付近にある中枢
(判断・命令をする神経細胞の集まり)。
橋は延髄の上に位置する中枢です。
二酸化炭素化学受容体は、
文字の通り
「二酸化炭素(の濃度)を受け止める」受容器です。
受容器がある橋や延髄自体が命令を出す呼吸中枢。
だから受容器と中枢がごく近くにある反射になりますね。
具体的に確認しましょう。
血液中の二酸化炭素濃度が高くなってきたことを、
二酸化炭素化学受容体が感じ取ります。
その情報を受け取った橋や延髄が、
「二酸化炭素増えてる!
呼吸して二酸化炭素を吐き出して!」と
呼吸筋群に命令します。
命令を受け取った横隔膜や肋間筋が収縮して、
「呼吸」をするのです。
ただ、普段から二酸化炭素をうまく吐き出せない人だと、
今説明した「二酸化炭素化学受容体」の情報では
うまく呼吸できません。
血液中に二酸化炭素が多い状態に体が慣れてしまったからです。
でも、呼吸はしないと全身の細胞に酸素が届きません。
だから大動脈など太い血管にある
「酸素化学受容体」の出番です。
こちらも具体的に確認です。
酸素化学受容体は、
血液中の酸素濃度が低くなってきたことを感じ取ります。
「酸素足りなーい!」の情報が、橋や延髄に届けられます。
情報を受け取った橋や延髄は、
「なぬ!ちゃんと呼吸して!酸素取り入れて!」と
呼吸筋群に命令ですね。
あとは命令を受け取った呼吸筋群が収縮して、呼吸です。
ここで注意!
この酸素化学受容体からの情報に
呼吸中枢が慣れている状態の人の体の中に、
いきなりたくさんの酸素が入ったらどうなるでしょう?
酸素がたくさん(血液中の酸素濃度が上がる)なので、
酸素化学受容体からの情報で呼吸中枢は動きません。
そもそも二酸化炭素が多い状態に体は慣れてしまっていますから、
二酸化炭素化学受容体からの情報でも呼吸中枢は動きません。
つまり、呼吸が止まってしまうのです。
これが「CO2ナルコーシス」と呼ばれる怖い状態です。
酸素ボンベを使う人に、
決められた量以上の酸素を流してはいけない理由ですね。
看護実習に出ると必須レベルで必要になる基本理解です。
今のうちに、
そのメカニズムと怖さを頭に入れてくださいね!
【今回の内容が関係するところ】(以下20220822更新)