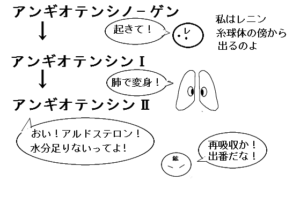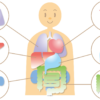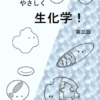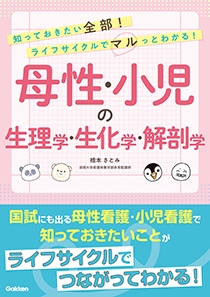11 ホルモンのおはなし(10)
副腎皮質ホルモンの、ちょっと詳しいおはなしです。
今回は、鉱質コルチコイドのアルドステロンについて。
ミネラルコルチコイドとも呼ばれるように、
腎臓に作用して、
血液と尿のミネラルを調節するホルモンです。
ミネラルのうち、
特にナトリウムとカリウムに対して働きます。
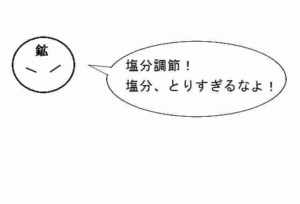
大事なことを覚えてしまいましょう。
「レニン・アンギオテンシン・アルドステロン系は、
血圧を上げたいときの呪文」です。
血圧を上げたくなったら、
「レニン・アンギオテンシン・アルドステロン!」ですよ。
何が起きているのかを説明しますね。
血圧が下がると、
腎臓に流れ込む糸球体(血管ですね)の傍ら(かたわら)にある
「傍糸球体装置」がそれを感じ取り、レニンを出します。
レニンはアンギオテンシンのもと
「アンギオテンシノーゲン」を起こして、
アンギオテンシンⅠに変えます。
起こされたばかりのアンギオテンシンⅠは
まだ寝ぼけているので、
肺でアンギオテンシンⅡへとしっかり起こしてもらいます。
しっかり目覚めたアンギオテンシンⅡは、
アルドステロンに「おい、血圧低いってよ!」と呼びかけます。
これでアルドステロンが
原尿からナトリウムイオンを引き込みます。
ナトリウムイオンは水と仲が良いので、
ナトリウムイオンと一緒に
水分も毛細血管内に再吸収されます。
血管内に水分が増えたので、
血管にかかる圧力が上がります。
これで、血圧が上がるのです。
もっとも、血圧を上げるだけなら
下垂体後葉のバソプレッシンのほうが直接的。
アルドステロンは、
「ミネラル(イオン)の出し入れ」に注目してください。
先程は血圧が上がる機序に注目しましたが、
もう少しミネラルの動きに注目しましょう。
アルドステロンが働くことで、
尿細管中の原尿から体内に
ナトリウムイオンと水を再吸収していました。
でも、これで終わってしまっては
体の中がプラスに傾いてしまいます。
ナトリウムイオンはNa+だったからですね。
だから代わりに血液からカリウムイオン(K+)
を尿細管内に出してあげます。
プラスを再吸収して、プラスを分泌すれば、
体のプラスマイナスはうまく維持できそうです。
これはアルドステロンの大事なお仕事!
血液中カリウムイオン濃度が高くなると
心臓が止まってしまうこと、
ミネラルのところでおはなししましたよね。
そんなことにならないように、アルドステロンは
血液中のカリウムイオンを
原尿経由で体外に排出しているのです。
カリウムイオンがどちらに多くて、
どんな働きに関係しているのか。
忘れてしまった人は
「9 ビタミンとミネラル」を復習ですよ。
【今回の内容が関係するところ】(以下20220607更新)