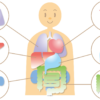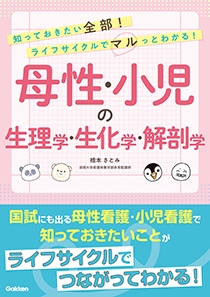2 薬に共通するおはなし(1):吸収(A)の応用(5)
錠剤…といっても、目的に合わせていろいろありますよ。
一番単純なのが、
薬に形を整えるためのデンプン等を加えただけの裸錠(素錠)。
ただ、これではひどく口当たりの悪い(苦い!)薬が
できることがあります。
それはよろしくないので。
裸錠の表面をフィルムで覆ったものがフィルムコート錠。
これなら苦い薬も一安心。
飲みやすさという点でもう一歩進んだものが糖衣錠。
フィルムではなく糖衣(砂糖)で覆ってありますので、
口に入れると甘味を感じます。
子供にとって、とても飲みやすくなりましたね。
ただ、覆っている糖衣がなくなると、
急に本来の薬の味(苦味等)が出てきます。
いくら口当たりがいいとは言っても、
すぐに飲み込まないとダメそうですよ。
裸錠の表面を腸で溶けるセルロース等で覆ったものが腸溶錠。
胃の酸に弱く、
裸錠では小腸に到着する前に分解されてしまう薬も、
腸溶錠にしてしまえば安心ですね。
ここまでは、薬の表面に注目してみました。
せっかくです、
錠剤の内側も見ていきましょう。
錠剤の内側に工夫をする理由、
それは「ゆっくり長期間効かせる」ためです。
飲みやすい錠剤と言えども、
「毎食後3回」よりは「1日1回」の方が楽ですよね。
単純に3倍の量の薬を一度に体の中に入れたのでは、
体の中の薬の量が多すぎて、
体にとって「毒!」になってしまうかもしれません。
だから、
徐々に薬が出ていく薬(徐放剤)が必要になるのです。
単純に溶ける速度を変えて(混ぜるものの比率を変えて)
1つの錠剤にしたもの(スパスタブタイプ)。
早く溶ける部分で
遅く溶ける部分をくるんだもの(ロンタブタイプ)。
遅く溶ける部分の表面を腸で溶ける膜でくるんで、
さらに早く溶ける部分で包んだもの(レペタブタイプ)。
他にもベース(基盤)になる部分に小さな薬を埋め込み、
消化管内で徐々に溶けだすようにしたものもあります
(グラデュメットタイプやマトリックスタイプ)。
その薬の特徴や効かせ方によって多くのタイプがありますが、
共通するのは「薬を飲む回数を減らす」ことです。
もちろん、
前回おはなししたカプセルにも徐放型のものはありますよ。
一番外側のカプセルはそのまま。
中に入れる薬の「粒」にちょっと工夫を。
胃で溶ける粒と
腸で溶ける粒の2種類を入れるもの(顆粒型カプセル)。
もっと細かく薬の表面を加工して、
溶ける順序を付けたもの(スパンスル型カプセル)。
粒の表面をセルロース等で覆い、
徐々に溶けていくようにしたもの
(拡散徐放型カプセル)などです。
次回、錠剤の注意点についておはなししますね。
【今回の内容が関係するところ】(以下20221108更新)