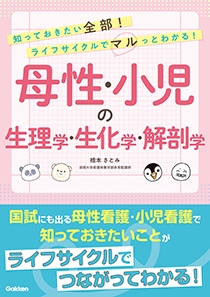8 各論3:体温(消化器系):小腸・大腸(2)大腸(2:下痢と便秘2)
下痢のときには「腸管保護」も大事です。
タンニン酸アルブミンをご紹介しましょう。
https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00009526
この薬は広がった腸管を適度に収縮させつつ、
表面に膜を張って粘膜を守ってくれます。
一般的な下痢に、広く使われますね。
禁忌は出血性大腸炎と牛乳アレルギーのある人。
出血性大腸炎は「O157:H7」に代表される
病原性大腸菌による、出血を伴う大腸炎です。
ヒトの体に悪さをするのは、
病原性大腸菌が作った毒素(主にベロ毒素)。
菌自体が悪さをするわけではないので、
抗生物質を飲んでも下痢はじめ症状は良くなりません。
しかも他の不具合が起こるリスク
(溶血性尿毒症症候群など)が上がってしまいます。
こんなときには、毒素(とそのもとになる菌)を
下痢で体の外に押し出してしまうしかないのです。
むやみに下痢を止めてはいけない理由です。
ウイルス性下痢の代表、牡蠣等によるノロウイルスも
同様に体外排出しかありません。
こちらは毒素ではなく、ノロウイルスの存在自体が
小腸上皮細胞をボロボロにしてしまいます。
とにかく「出してしまうこと」が全てです。
タンニン酸アルブミンの「アルブミン」は牛乳由来。
牛乳アレルギーのある人の体内に、
わざわざ牛乳タンパク質を入れてはいけませんね。
タンニン酸アルブミンの原則禁忌は細菌性下痢。
理由は…先程の出血性大腸炎のおはなしと同じです。
細菌を外に押し出す大事な手段を、
止めてしまってはいけませんね。
では自律神経系異常の下痢だったらどうか。
腸管はじめ消化器系は、
副交感神経系のコントロールを主に受けています。
大腸の腸管運動(蠕動)が活発すぎると、
水分を吸収する間もなく、便が通り過ぎていってしまいます。
ちょっと副交感神経系をお休みさせる必要がありそうですね。
こんなときに使うのがロペラミド(ロペミン)です。
https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00051670
副交感神経系副交感神経系の受容体に働いて、
その活動を邪魔します。
結果、腸管の平滑筋が緩んで、
水分を吸収する時間を作れることになります。
ちょっと補足しておきますね。
「腸管」と一言で言いましたが、小腸と大腸はかなり広いですよ。
いくら迷走神経が副交感神経系の消化管担当とはいえ、
やはり一人ですべてをこなすのは大変そうです。
だから、ヒトは腸管のコントロールを
神経の集まり(神経叢)にもしてもらうことにしました。
小腸と大腸の筋肉コントロール専門、
アウエルバッハ神経叢です。
アウエルバッハ神経叢には、
迷走神経からの情報を受け止めるところがあります。
今回のロペラミドが働くμ受容体がその一例。
ロペラミドの副作用に嘔吐や口内乾燥といった
消化器系抗コリン作用が出ることからも、
迷走神経(副交感神経系)との関係が分かるはず!
ロペラミドは、
「オピオイド受容体作動薬」とも呼ばれます。
オピオイドは、
鎮痛・陶酔作用を持つアルカロイドと呼ばれる化合物のこと。
ケシの実由来の天然物から、人工的に作ったもの、
ヒト体内で作られているものまで多くの物を含む言葉です。
これについては「呼吸」ブロックの中枢…
麻酔のところで出てきます。
【今回の内容が関係するところ】(以下20230318更新)