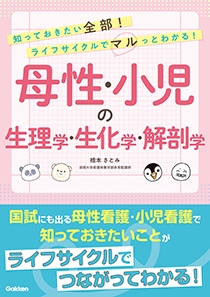10 各論5:体温(感染・免疫):②細菌に効く薬(6)
続いて結核菌に効くお薬(抗結核薬)。
結核菌は他の細菌と違い、細胞壁がちょっと特殊。
普通の抗生物質では効きません。
しかも中途半端に対処してしまい、
体内に菌を残してしまうと長い年月を経て
全身に病巣を作ってしまいます。
だから耐性菌を作る暇のないよう、
効く薬を4種類一緒に飲んで、
徹底的にたたくことが原則スタイル。
飲み忘れのないよう、
しっかり薬を飲み切ることができればちゃんと治せます。
効く薬の一例として、
リファンピシン(リファジン)を紹介しますね。
https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00058339
結核菌のRNAを作る酵素
(RNAポリメラーゼ)を邪魔する薬です。
これまたびっくりするくらい禁忌が多いですね。
やっぱり他の薬でも分解担当になっている
肝臓の酵素を代謝に使っているせいです。
禁忌の数に負けずに、
落ち着いて目を通してみましょう。
これら禁忌の理由は、
抗ウイルス薬をはじめとする「一緒に飲む薬」の
働きを弱めてしまうことが原因です。
ただ、高脂血症の薬(ぺマフィブラート)の効果は
強く出てしまうので、ここには注意ですね。
あとは胆道閉塞や重い肝障害があっても禁忌ですよ。
併用注意を含めると、
薬の効果が強まるものも弱まるもののもっと増えます。
血中濃度のチェックはもちろん、
何かのサインが出ていないか見逃すことのないように!
結核菌のように特殊な扱いを必要とするものに
「芽胞菌」があります。
これは1つの菌ではありません。
芽胞という休眠形態をとれる菌をまとめて、
「芽胞菌」と呼んでいます。
ボツリヌス菌、破傷風菌、
ディフィシルが含まれますね。
ボツリヌス菌は食中毒の菌。
破傷風菌は、
ワクチンのところでおはなししますね。
ディフィシルは、
抗生物質のせいで起こる偽膜性大腸炎の原因菌でした。
芽胞の形になってしまうと、
原則として菌を殺せなくなってしまいます。
眠っている状態なので、
増殖しない以上問題ないように思えますが…。
いつ休眠から目覚めて増殖を始めるか分からないのでは
困ってしまいます。
特に手術時では大問題です。
だから手術器具は「滅菌」する必要がありますね。
滅菌は字の通り「菌を滅する」こと。
芽胞を作る菌(の芽胞まで)も滅するためには
特殊な条件が必要です。
例えば高温高圧滅菌(オートクレーブ:121℃、20分)や
EOG滅菌(エチレンオキサイドガス)、
ガンマ線滅菌などがあります。
でも、ヒトの皮膚にはこれらは使えません。
使ってしまったら、皮膚の細胞が全滅してしまいます。
だから、ヒトの体には
「滅菌」ではなく「消毒」です。
病原微生物を死滅または病原性を除去して、
感染の危険をなくすことが「消毒」です。
「殺菌(菌を殺す)」というのは、
滅菌と消毒を含む概念ですね。
「静菌(菌を静める)」は、
「除菌(取り除く)」と
「抗菌(増えるのを防ぐ)」を含む概念ですよ。
次回は消毒薬についておはなししますね。
【今回の内容が関係するところ】(以下20230503更新)