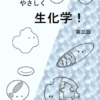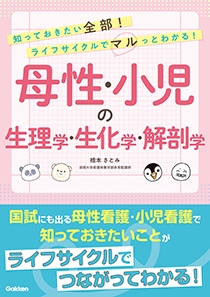4 消化器系のおはなし(1)
消化器系の目的は、
「栄養を体の中に取り入れ、
いらなくなったものを体の外に出すこと」です。
何がヒトにとって必要で、
食べ物から取り入れなくちゃいけない「栄養」かは、
ある程度は「生化学」にお任せします。
三大栄養素(炭水化物・タンパク質・脂質)については
「3 糖質のおはなし」~
「8 脂質代謝のおはなし」に説明があります。
「9 ビタミンとミネラル」では、
それ以外の成分についておはなししてあります。
なぜそれが必要なのか、足りないとどこがおかしくなるのか。
そして捨てるときは単に「ぽいっ!」でいいのか。
ちゃんと読んで、理解しておいてくださいね。
さて、前置きはここまでにして。
まずは口から小腸までの吸収編です。
消化器系は「栄養を吸収する」という
とても身近なおはなしです。
だからこそ、
しっかり理解してほしいところでもあります。
あとは肝臓・膵臓・腎臓についても
随時おはなししていきますからね。
最初に意識しておいてほしいこと。
消化器系は、ただの管ではありません。
消化器系がしなくちゃいけないことは何でしたっけ?
「栄養を吸収する」でしたね。
そのためには「(吸収できるところまでに)
吸収できる形にしておくこと」も必要。
だから、栄養を吸収するところ「小腸」では
「栄養吸収スペースを限られた体腔内で
できるだけ広くとる」工夫がされています。
それが小腸上皮細胞の構造。
やたらと凸凹がたくさんありますよね。
凸凹には、表面積を広げる働きがあります。
凸凹がたくさんあるということは、
小腸の表面積はかなり広いということ。
表面積を広げて、
やってきた栄養を余すところなく吸収しようとしているのです。
もちろん、そこに着くまでに
「吸収できるサイズ」にしておかないと意味がありません。
物理的に細かくする代表が「歯」。
化学的に細かくする代表が「(各種の)消化酵素」。
だから、私たちは歯の重要性について勉強し、
消化酵素の名前を勉強しないといけないのです。
どこから出て、何を分解してくれるのか。
そこがおかしくなると、
どんな栄養の吸収に不具合が出るのか。
丸暗記なんかではありません。
「ここから出る、これがおかしいと、
これこれの吸収がうまくいかない。
そうすると、体のどこどこの成分だから、
あそこが悪くなるかも…」
こんな風に理解してつなげていくのです。
ここまでできれば「暗記!」は減って、
質問のされ方が変わってもちゃんと答えられるようになります。
応用問題も怖くなくなりますよ!
では、次回から
消化器系を部分ごとに見ていくことにしましょう。
【今回の内容が関係するところ】(以下20220912更新)