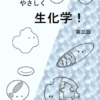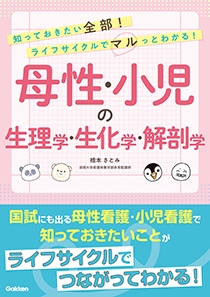12 各論7:呼吸(中枢・精神):⑥パーキンソン病の薬(7)
不随意運動の後半。
あまりお目にかからないはずの不随意運動の例として、
「振戦」、「チック・トゥレット」、「静座不能(アカシジア)」、
「舞踏運動(コレア)」、「アテトーゼ」、「バリスム」、
「ジストニア(ジストニー)」があります。
振戦というのは、反復性のあるリズミカルな運動。
プルプル、ブルブルといった小刻みな動きで、
安静時に出ると分かりやすいですね。
運動時(動かそうとしたとき)に出ることもありますよ。
例えば慢性アルコール中毒の人で
「飲まないと手が震える…」のが振戦です。
小刻みな動きという意味で近いのが「チック」。
チックは突発的かつ不規則な、
体の一部が素早い動き(や発声)を伴うもの。
チックの中でも
声と特定行動が主に出るものを「トゥレット」と呼びます。
ため息のような静かなものから、
相手に聞こえるうなり声、
汚言症(シネ、バカ等々)までありますよ。
行動もしかめ面のような表情変化から
他人に触ることまでも含み、結構多種多様です。
手足に不随意運動が出る例として、
下肢がむずむずして座っていられない「静座不能(アカシジア)」。
まるで踊っているかのような「舞踏運動(コレア)」。
たこの足のようにゆっくりと動き続ける
「アテトーゼ」などがあります。
特に激しく手足を投げ出してしまう
「バリスム」は、骨折の危険があるので要注意!
あとは、持続的な筋肉の緊張で姿勢が変になってしまう
(そして反復性運動が出る)ものが「ジストニア(ジストニー)」。
首が片方に傾いてしまう痙性斜頸や、
書くときだけ姿勢が変になり変な力が入る書痙などがありますよ。
これらの不随意運動を一言でまとめてしまうと、
「ジスキネジア」になります。
不随意運動の簡単なまとめ、一段落。
パーキンソン病とそこに効く薬の理解が深まったところで、
パーキンソン症候群のおはなしです。
パーキンソン病は
神経伝達物質のドーパミンと深い関係がありました。
ドーパミンは、
他の病気の薬によって影響を受けてしまうことがあります。
例えば、この次に出てくる統合失調症の薬の一部は、
ドーパミンの受容体をブロックします。
すると「ドーパミンが不足した」のと同じ状態になりますから…
パーキンソン病に似た症状が出てくることがあります。
これがパーキンソン症候群です。
細かい分類は、今は気にする必要はありません。
まずは薬のせい(薬物性)と
中毒のせい(中毒性)で起こりうるんだ…と
分かってくれればいいですからね。
【今回の内容が関係するところ】(以下20240128更新)