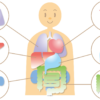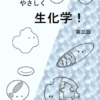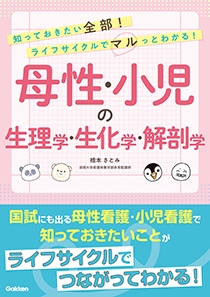3 薬に共通するおはなし(2):分布(D)(4)
相互作用のおはなしを「吸収」からスタートです。
相互作用は
体の中にある「他の物」との関係で起こるもの。
他の物のせいで吸収が変化する例として、
消化管の働きを良くするプリンペランと、
鎮痛剤のアセトアミノフェンの相互作用があります。
何だかおなかの調子が悪くて、
痛みがある状態をイメージしてください。
「お腹の調子を良くする」のがプリンペランで、
「痛みを止める」のがアセトアミノフェンですね。
薬を飲む立場からすれば、
両方飲んですぐによくなりたいところですよね。
この2つを一緒に飲むと、プリンペランが
アセトアミノフェンの吸収を(必要以上に)促進して、
アセトアミノフェンの働きが
予想よりも強く出てしまいます。
効きすぎはよいことではなく、
悪いこと(副作用)が起こることはご存知の通りです。
薬どうしでなくとも相互作用は起こりますよ。
グレープフルーツの果汁は、
小腸に上皮細胞にある薬を分解する酵素を邪魔します。
その酵素のせいで吸収時に一定量分解されていた薬は、
グレープフルーツ果汁と一緒に飲むと吸収される量が増えて
予想よりも「効きすぎる!」ことになりますね。
降圧剤として使われるカルシウム拮抗剤や、
免疫抑制剤として使われるシクロスポリンがその例です。
血圧が異常に高いときに、
カルシウム拮抗剤を飲むと血圧は下がります。
薬が効きすぎて血圧が下がりすぎたら、
今度は血液が届いてほしいところまですらも
血液が届かなくなってしまうかもしれません。
また、移植のときには
移植する部分(皮膚や臓器など)に対して
「異物!」と白血球に認識されないように
シクロスポリンを使います。
ここで必要以上に免疫抑制されてしまったら、
外部から入り込んだ病原体(微生物)さえも異物と認識せず、
重い感染症を引き起こしてしまうかもしれません。
どちらも、重い相互作用です。
逆に相互作用で吸収が減る例は、
高脂血症の薬クエストランと血栓を防ぐ薬のワーファリン。
クエストランが、ワーファリンの吸収を邪魔してしまいます。
血液中の脂質が多い(高脂血症)と、
血管の内側で粥状硬化が起こりやすくなります。
粥状硬化した部分が傷ついて出血すると、
かさぶた(血栓)ができて、
それがはがれて血管に詰まってしまったら
血栓になってしまいますね。
これまた一気に対処したいところですが…
一緒のタイミングで飲んでは望んだ効果は出ませんね。
せめて4~6時間間隔を開ける等の工夫が必要です。
「面倒だから一緒に飲んじゃえ!
…ちゃんと飲んでいるのに、効かないぞ?」
これでは、薬を飲む意味がありませんからね。
【今回の内容が関係するところ】(以下20221119更新)