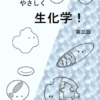3 薬に共通するおはなし(2):分布(D)(8)
アレルギー(過敏症)のおはなしは、
生化学の第1章でもおはなししましたね。
花粉症はⅠ型アレルギーと紹介した、
細胞小器官(分泌顆粒)大活躍のところです。
白血球が薬を「異物!」と認定してしまったものが
薬アレルギー(薬剤過敏症)。
Ⅰ型からⅣ型まであることや、
白血球の種類も生化学の1章と同じおはなしです。
復習がてら確認していくことにしましょう。
Ⅰ型アレルギーは即時型。
一度異物と認定されたら、
すぐにIg-Eを介する免疫反応が起きて炎症が出てきます。
肥満細胞の中に貯め込まれた分泌顆粒の中身、
ヒスタミンのせいですね。
ヒスタミンが働くところは、
鼻腔粘膜・涙腺
(鼻水や涙を出させる)だけではありませんよ。
気管支に働くと、気管支がギューッと狭まります。
血管に働くと、
血管は拡張して血管透過性が亢進します。
炎症部位へ白血球が集まりやすいようにしているのですね。
その結果がぜんそく(様の呼吸困難)、
血圧の低下(ひどくなるとショック)です。
食物・ハチアレルギーで怖いアナフィラキシーショックの、
「ショック」です。
アナフィラキシーショックを起こしたときに、
一刻も早く使う必要のあるアドレナリン注射のおはなしは
注射薬(筋肉注射)のところでしましたよ。
Ⅳ型アレルギーは遅効型(遅延型)。
Tリンパ球が働くので、
24時間(1日)以上たってから炎症が出てきます。
注射薬の皮内注射の例に出した、
結核に対する免疫反応(ツベルクリン反応)が代表例。
他にも薬に触れたところが炎症を起こす
「接触性皮膚炎」もⅣ型。
抗生物質軟膏(塗り薬)や
洗剤・化粧品等で起こる可能性があります。
Ⅳ型は皮膚に症状が出ることが多いのですが、
「皮膚に不具合が出たからⅣ型!」ではありません。
じんましん(赤いぼつぼつ)、
光線過敏症(光にあたると赤みやかゆみ)、
多型紅斑型発疹(形は決まっていない、赤み)などは、
Ⅰ型アレルギーとして出ることもあります。
しかも塗り薬だけではなく、
飲み薬等で薬が体の中に入ってから出ることもあります。
「皮膚に症状が出たらⅠ型のこともⅣ型のこともある!」
これ、忘れないでくださいね。
Ⅱ型とⅢ型は免疫応答の内容が似ています。
働く白血球の違い(Ⅱ型はマクロファージ、Ⅲ型は好中球)と、
場所の違い
(「血管内」とあったら、Ⅲ型が多い)で見分けましょう。
肝臓や腎臓で悪さをすることが多いので、
Ⅰ型でもⅣ型でもないときには
薬アレルギー(薬剤過敏症)の
Ⅱ型・Ⅲ型も疑ってくださいね。
以上で分布についてのおはなしが一段落。
ようやく効いてほしい細胞の前まで薬が届きました。
次回から、「薬の働き」についてのおはなしです。
【今回の内容が関係するところ】(以下20221119更新)